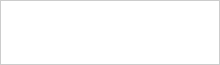海外視察研修 2025 報告書
学部時代からの夢だったバネラ長澤駐在員アテンドのこのツアーに念願かなって参加することができた。フルタイムの博士課程学生はかなり珍しいと思うが、それもそのはず、臨床工学技士資格を持つ博士人材は極端に少ないうえ、そのほとんどが社会人大学院生としての在籍であるためである。そんなことはさておき、今回は(少なくともホームページにあげる分は)字数制限がないらしいので、現地での日記形式で記載する。皆様にも行った気分でお楽しみいただければ幸いである。
・参加の動機
母は英文科、父は米国留学経験ありという英語に慣れ親しんだ環境で幼少期を送ったこともあり、かねてより国際活動に興味があり、「国際会議に行ける研究室」というどうしようもない理由で卒業研究の研究室を選んだくらいのどうしようもない人間である。このツアーの存在は学部時代から知っていて、臨床工学技士になったら絶対に行くぞと楽しみにしていた。しかしながら本当にどうしようもない人間だったので、大学時代は単位を取りこぼして4年で臨床工学技士免許が取れず、修士課程になってから国家資格を取り、当然技士会加入も1年遅れたわけである。したがって私の技士会加入は2022年であり、まだコロナ禍の影響が完全に抜けきらず、ツアーも現地開催中止となっていた。
時を経て現地開催が再開したときにはすでに私は医学博士目指して4年制の博士課程に在籍していた。さらに言えば私の優柔不断な性格のせいで、臨床工学研究と学位研究となる医学研究を在籍ラボにさんざんご迷惑をおかけしながら続けている最中であったが、いつまでもその状況を続けるわけにもいかず腹をくくらなければならない時期に差し掛かっていた。
そんなわけで今後の成り行きを決めるためにも、「現職の研究領域と慣れ親しんだ臨床工学領域、どちらも世界を見てから決めよう」というのは博士入学早々に決めてはいたが、昨々年、昨年のツアーは実験の立ち上げがあり日本を離れることができなかった。実は今回も実験の立ち上げはかぶっていたが、就職前、また学位論文投稿先のグレードを将来の選択によって決める大切な時期だったこともあり、「就職前にどうしても世界水準の臨床工学を知りたい」「そのためには3年生の今がラストチャンス(*医学博士は4年制なため就職活動は翌年である)」ということで、申し込みを行った次第であった。すでに自身の学位研究領域の世界水準を見物するためにドイツへの研修を企画し、しかもそれから1カ月半後という短期間での連続した海外研修だったために指導教員は大いに渋い顔をしていたが、無事招聘の連絡があり飛び上がるほど喜んだのは言うまでもない。
・参加準備
私の場合すでに国際会議への出席経験や、単身での渡航経験があったため、ESTA申請やAAMIへの参加登録についてはかなりスムーズであったように思う。しかしながらフルタイムの学生であるため、いかんせん金がないのである。さらに円安がその事態の深刻さに輪をかけていた。実際当初招聘予定だった皆様も金銭的な理由から辞退されてしまうなど、その深刻さはツアーの継続事態を危ぶむものだろうことは想像に難くない。私の場合は博士人材生活費支援の一環としてJST SPRINGという制度から研究費および生活費の支援を受けており、その一環で国際活動支援というものがあったので申し込んでみた。申請書の記載もさることながら、現在の学位研究と全く関連がない研修なので説得にはかなり難渋し、審査も難渋したがどうにか32万円の支援をいただくことができた。
金銭面の問題が解決したら身体面の問題である。アメリカは医薬品の持ち込みや航空機への積載が欧州に比べるとかなり厳しい。私の場合膠原病で抗リウマチ薬の自己注射が必要なため、ドイツ渡航に合わせて英文診断書の申請を行った。ドイツでは保冷用の冷蔵庫がなく、盗まれる不安におびえながらレセプションで預かってもらったが、今回はポータブルの冷蔵庫も持参した。航空会社から指示があったのでアメリカ大使館CBP部門に持参可能か確認を取って、無事OKとのことだったので大手を振って持参することとなった。そのほか注射器の廃棄ボックス、飲み薬も余裕を持つと約100錠となり、旅慣れたいつもの準備とはいえ「病気があるとスーツケースのスペースで損をするなあ」などと思いながら出発した。
・1日目

羽田に到着した。冷蔵庫の入ったスーツケースの重量は11キロ。12キロまではお土産が買えるかと皮算用をしながら預け入れた。同室同世代の梅崎さん(以下梅ちゃん)と学会でかわいがっていただいている国際交流委員の平山さんと合流し、機内へ。一週間前に航空会社から入札アップグレードの申し込みなるメールが届き、張り切って応募したが落選したので、ヒューストンまでエコノミークラスで向かった後乗り継ぎである。ヒューストンまでの機内ではボヘミアンラプソディーとトップガンがやっていたので気分を高めるために視聴し、比較的すぐに眠るようにした。
そんなこんなで長いフライトを乗り越え無事到着した。ヒューストンの空港でバネラ長澤駐在員(以下バネラさん)とも合流でき、英語の勉強がおろそかな私は一安心である。ニューオリンズの空港から出ると大変蒸し暑く、バネラさんと私の眼鏡が曇った。空港からコスコ(コストコ)へ向かい、任天堂スイッチ2の棚をしり目にラボへの土産をさっそく調達した。その後一度荷物をホテルに置き、時差ボケ防止のために今すぐにも眠りたい気持ちをこらえて再度バネラさんおすすめのテキサスロードハウスへ。時差ボケも多少ありあまりたくさんは食べられなかったが、日本では物価高で鶏肉ばかり日本で食べていた私は久しぶりの肉に舌鼓を打った。非常に楽しい旅の幕開けである。
・2日目

図1:スプリンクラー設備
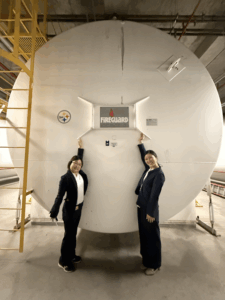
図2:非常用電源駆動用ガソリンタンク
朝から病院見学であった。バネラさん運転の車に乗り、LSU Hospitalへ。VIP用の駐車場に停めさせてもらい、会議室で少し病院について伺った後病院見学がスタートした。まず初めは非常電源やスプリンクラー設備の見学である。この病院は10年前のハリケーン「カトリーナ」の被害を受けたこともあり、災害対策に力を入れている。そのため非常電源設備が大変充実していた。日本と違ってすべてが大掛かりな装置で、大変驚いたのは言うまでもない。私はこのあたりの専門家ではないので、ただ「大きいな」という感想しか抱けなかったのが残念である。やはり勉強である。
そのあとは熱傷センター(Burn Center)やER(こちらでは救急部、という意味のEDが一般的な呼称である)や透析、がんセンターを見学させていただく。ニューオリンズ地区の基幹病院としての役割があるため、すべての状況に対応できるようになっている印象である。
なお、日本にも熱傷センターはあるが数が少なく、また厳密な無菌管理下に置かれているため、見学したことがある者はそう多くはないであろう。私も実習先にあったが、センター内には入っていないため、実際のユニットを見学するのは初めてであった。水療法(日本ではデブリードメントと言ったほうがいいだろう。やけどで傷ついた皮膚を取り除く治療である)の部屋にはカラオケ設備やテレビ迄ついていて、ペインコントロールや快適で痛みの少ない治療に対しての意識の違いを見せつけられた。

図3:熱傷センターの水療法室。レーザーも数種類設置されており充実した設備である

図4:アメリカの透析用コンソール

図5 : 食料品保管庫がある
透析室ではほとんどの患者がバスキャスを挿入しており、浴槽文化がないからかな?と思ったりした。真偽のほどはわからないが、もし海外の透析事情に詳しい方がこれを読まれたならば教えていただきたい。なお、機器のサイズやダイアライザのサイズは日本とほぼ変わらない。欧米人の体格を思うと少々意外である。
がんセンターでは生活困窮者が再発しないよう、食事の支援やクッキングクラスもあるそうで、食事に対する意識の違いを垣間見た。アメリカと言えばジャンクフードのイメージがあった私には少々うれしいことだったが、滞在中の食事にはやはりはっきりした味わいの食事が多く、だしが恋しくなったのはまた別の話である。驚くべきは抗がん剤の副作用もほとんどないので、投与中も飲食が可能だという。大きなマフィンをさもおいしそうに食べる患者さんを見ることができた。素晴らしい。
ERはニューオリンズでも有数の外傷センターがある。中でも化学テロに備えた洗浄室は実際に水が出ているところをみられた。今後も実用されないことを祈る。
その後会議室に再び戻りIT部門の管理者の話や臨床研究の状況のお話を聞いた。聞けばマウスのカーソル移動迄監視されているらしく、しっかり情報管理が行き届いている印象を受ける。プライバシーに関する意識も高く、たとえ家族のカルテであっても担当チーム以外が閲覧することは許されないらしい。臨床研究はやはりアメリカのスパンの速さを見せつけられ、制度上の改革が必要だなと感じることが多かった。治験情報はFDAの一括管理ですべてが見られるそう。日本では病院など様々な機関のサイトを確認しなければならないので、うらやましい。
午後はオペ室である。オペ室のレイアウトは日本と変わらないし、手術台も日本と変わりない。欧米人の体格を思い起こして「なるほどだから英語でtableというのか」などと一人得心していた。機材のレイアウトはあまり日本と変わらない印象であった。
Tシャツやマルディグラビーズ(ニューオリンズの有名なパレードである。街中ではこの際にフロートから投げられるビーズがたくさん土産として売られている。翌日以降のAAMIでもたくさん配っていた)などたくさんのお土産もいただき、うれしい気持ちで病院を後にした。
その後AAMIのレジストレーションを行った。始まる前はジャズバンドが「聖者の行進」や「You are my sunshine」などを演奏していて参加者も合唱するシーンがありワクワクした。アメリカでは古い洋楽が流れている場合も多いので、最新の洋楽のみならずベーシックな洋楽もたしなむと文化的にも楽しめるであろう。なお、私はレジストレーション用のQRコードを忘れていたが名前を入れて無事スムーズにレジストレーションできたので今後参加される方も落ち着いて対応してほしい。(もはやバネラさん含めメンバーにさえ悟られなかった)この日は夜にAAMI主催のミシシッピ川クルーズディナーパーティーに申し込んでいたが、抽選に外れてしまったのでカンファレンスセンター近くでCrowfish(ザリガニ)を食した。初めて食べたが臭みがなくおいしかった。エビのような味わいである。もしかしたらきれいな水で養殖されているのかもしれないが。
・3日目
AAMIが本格スタートした。朝はkeynoteを聞く。これは国際会議でよくある形式で、日本語で言うなら基調講演という感じのものだ。国内の会議の場合、日本人のまじめさがよく出たものが多いが、国際会議の場合デモあり、なんでもありのにぎやかな雰囲気で行われて結構楽しい。今回もご多分に漏れず、まるでディスコのような雰囲気の中開催された。演題は子ども向けのロボットについて。日本でも最近子どもに本物の医療道具などを使ってこれから受ける治療について説明するプレパレーションという手法(興味がある方は小児科学会などに行くとたくさん演題が出ている)が小児医療で行われるのが一般的になってきたが、アメリカのそれはさらに進んでいて、子どもの感情表出を助け多角的に子どもを支援していることが分かる。

図6:デモあり、なんでもありのkeynote会場
国際会議の場合ランチがバイキング形式の時とランチボックス形式の時がある。今回はバイキング形式だった。
そのあとにはお待ちかねのExpo(展示会)へ。展示会場は日本の学会だと結構敬遠する人も多い印象だが、展示会場は知り合いが増える絶好のチャンスなので日本でも学会の展示会場には必ず足を運ぶ。今回はバネラさんにより実に多くのAAMI関係者やACCE関係者を紹介してもらうことができた。前日見学したLSU hospitalの関係者もおり、やや時差ボケ気味で見学したため覇気がなかったのか、「Are you sleeped?」と言われてしまう大失態であった。海外では質問をしなければその場にいないのと同じことになる。せっかくたくさんの人にお世話になったのだからすべての病院関係者に質問しておけばよかったと思った。
若干の反省をもって夜はAAMIのパーティーへ。なんだか夜には翌日「invitation only」のパーティーに紹介してもらえる話になっていた。私は今回スーツケースの容積を減らすためにドレッシーなものを何も持ってきていなかったので、若干冷や汗をかきながらバネラさんが話を進めるのを聞いていた。参加者の皆さん、急にパーティー参加が決まることもあるので、一定のキレイ目な格好はお忘れなく。帰国後さっそくたまったマイルでワンピースを購入したことは言うまでもない。AAMI、ACCE両者とも日本のこの小さなチームを大変歓迎してくださって、あたたかい雰囲気だった。私が学部1年で初めて国内の学会に参加したときに臨床工学技士の皆さんから感じたあたたかさに似たものを感じて大満足の一日であった。
・4日目
AAMI2日目。Keynoteを聞いた後expo参加という昨日と同じ流れをとった。この日のkeynoteは歯科領域に臨床工学の機器管理を入れては、という話だった。なるほど確かに歯科用のユニットは電気系統の塊だし、と妙に納得しながら聴講した。それこそ私の在籍大学(東京科学大学)などはもともと医系と歯系が共存しているのだからさきがけになれそうな気がする。帰国後考えをまとめることにしよう。
その後国際会議にまれにあるキャリアブースに行き、バネラさんに誘われて求職用の写真を撮ってもらう。こんなブースがあるのも国際会議ならではである。

図7 : キャリアブースでの風景
展示についても補足しておくと国内の学会と比べて企業がくれるノベルティが豪華な傾向にある。詳細はぜひツアーに参加して自身で感動を味わってほしいのだが、ひとまず私は敗れたTシャツの替えをたくさん手に入れ、これで夏服を買わなくて済むとほくそえんでいた。
その後は前日にバネラさんがセットアップしてくださったAAMIとACCEのパーティーをはしごした。楽しいひと時を過ごしたが、皆さんドレッシーで私だけまるでアヒルの子である。相方の梅ちゃんはもともとのセンスがあったのでさまになっていたが……。やはり国際会議には1枚はワンピースとおしゃれな靴を持参したいものである。翌日には帰る参加者もいるため、別れ際の合言葉は「See you in Denver」である。
その後はパーティーに参加していた日本人の先生からバーボンストリートに行きましょうと誘われ、夜のバーボンストリートでジャズを楽しんだ。ストリート全体がむせかえるようなにおいでエネルギッシュなひと時だったが、少し治安に不安がある場合もある。またこれはバーボンストリートに限らず、女性の場合海外では安心して入れるお手洗いが少ない場合があるので注意が必要だ。私と梅ちゃんは楽しく飲んだ後にトイレを探す羽目になり、マリオットホテルに助けられることとなった。
・5日目
AAMI最終日である。この日はホームケアのセッションに入り、各国の在宅医療について学ぶことができた。在宅医療はリソースが限られている分難しいが、各国IoTなどの技術を駆使しながら充実した医療を展開しているようである。エネルギッシュなセッションであった。
その後最後のkeynoteへ。AIと医療安全にかかわるセッションであったが、英語力不足で半分くらいしか理解できず、英語を勉強しようと固く誓う羽目になった。しかしすっかり刺激たっぷりだった私は本当に来年もデンバーへ行って今回のCEたちと約束を果たす気満々になっていた。
ところでいつもPh.D student(博士課程学生)として国際会議に行くと、日本での博士課程学生への扱いの差に驚く。そもそも学生ではなく研究者として扱われるので、展示会やパーティーで対等な込み入った話ができるのだ。日本では「教授の庇護下にある学生」として扱われるので、かなり大きな違いだ。私の場合国立研究所の共同研究員資格を持っているので、国際会議に出席するための航空券の予約で職種を入力する場合、Researcher(研究者)として入力するが、かなり手厚い対応をされる場合があり、一般市民にも研究者がステークホルダーとして浸透していることに毎回驚かされる。学会でも歓迎されるだけではなく、対等にお話しできるので、日本と比べるとできることが多い。日本の学会で物足りなく感じた博士課程学生はぜひ次は海外へ視野を向けてみてはどうだろう。
午後はフレンチクオーターへ。かわいいお土産があったが、expoのノベルティがだいぶ多く、帰国時の重量制限を気にしなければならないためあまりはかどらなかった。そして国際会議の後に毎回思っているが、無事今回も「デンバーで何が買えるか知らないけどとりあえずANAの上級会員になって荷物の重量制限を緩くするぞ」と固く誓った。

図8 : わに肉のフライ
夜ご飯は伝統的なガンボやジャンバラヤ。ケイジャンスパイスが効いていておいしかった。そのほかわにの肉もあった。わにらしくない淡泊な味わいである。「これも養殖か?」と思って手元で調べてみるとなんとミシシッピ川にはわにがたくさんいる模様である。ミシシッピ川自体は結構泥っぽい見た目をしているが、わにの場合臭みと水のきれいさはあまり関係ないのかもしれない。ともかく野生でこれだけ臭みがないのは素晴らしい。だからお土産にわにがあしらわれたものが多いのかと納得した次第だった。なお、ルイジアナ方面のエネルギッシュでのどかな暮らしは、カーペンターズがカバーしている「Jambalaya」という歌があるので機会があったら聞いてみてほしい。もちろん伝統的な料理の名前が出てくるほか、「Swap」「Bayou」といった土地の雰囲気も分かり、存分に楽しめる。
ホテルへの帰りはかわいらしい赤い路面電車で帰った。いかにもアメリカという感じの赤い路面電車に乗りながら、そういえば病院見学で見たスプリンクラーもこれと同じ赤色で、ちょっとかわいかったのを思い出した。
・6日目
まずは朝一番にVA病院へ。VAとは退役軍人のことである。つまり退役軍人のための病院である。日本には軍隊がないのであまりなじみがないかもしれないが、アメリカでは軍人は現役時代もリタイアしてからも非常に大切にされる。(空港でも軍人向けラウンジがあるほどである)
しかしながらいつも十分前には決められた集合場所にいるはずのバネラさんの姿が見えない。バネラさん実は前日に肩を痛めてしまっていたので、「もしや具合が」と心配していたら、ほどなくして現れた。体調に問題がなく安心するのもつかの間、冷や汗をかきながら「免許証とカードがなくなった」という。すわ警察かと思ったが、ほどなくして無事に見つかり予定通り病院見学ができることとなった。
ここでも搬送ロボットや建設中の病室、日本でいうところのMEセンターを見せていただいた。針捨てのボックスが大変大きく、日本のように医療従事者が運ぶタイプでないのには驚いた。日本では患者さんの体液が付いたものは今すぐ手放すような文化がある。ここは日本との意識の違いなんだろう。また、消毒したかどうかもIT管理されており、日本のように消毒薬の本数を数えたり消毒薬のボトルにラインを引いて確認したりするような事もないらしい。こういった細かい文化の違いが面白いのはもちろんのこと、ベッドのマットレスが日本に比べてよいものを使っていて、日本人なら二人くらい眠れそうなサイズのものが置かれていることにも驚いた。なお、医療配管はすべてビン式ではなくおねじ式である。日本でも手術室では導入されている場合があるが、一般病棟には設置されていないことが多いので実はじっくり見る機会が少ない設備である。
先に退役軍人について少々説明を加えておいていうのもなんだが、そこまで私はアメリカの軍事制度に明るいわけではないので質問も「患者は何人いるのか」といったありきたりなことになってしまった。先にアメリカ独特の文化や病院のバックグラウンドについて学んでおくとより楽しめるかもしれない。
午後は初日に外れたミシシッピ川クルーズのリベンジへ。蒸気船のスピードは意外と速く、風が気持ちよかった。ジャズの演奏を聴きながら、途中わにが姿をみせるシーンもあり充実したクルーズだった。なお、今回は時間と体力的に難しかったので訪問しなかったが、わにの見物だけを目的としたSwap Cruiseもあるので、わにが見たければそちらを。
翌日は早かったので、この日の晩ご飯がニューオリンズでの最後の食事になった。初日のテキサスロードハウスを再び食した。やはりここの肉はおいしい。
翌日は研究費の都合で一番安かったシカゴ経由の便を私だけ取ったので、シカゴ経由で帰ることになった。ニューオリンズの空港でチェックインしたら、「研究者ね。シカゴから羽田までは長いし、隣を空けておくわね。カンファレンスお疲れ様」といううれしいねぎらいの言葉とともに隣席をブロックしてもらって優雅に帰国した。
・参加しての心境の変化
私は臨床工学技士ではあるが、臨床をバックグラウンドとしていない。基礎医学のバックグラウンドができたため、将来の方向を決めるために参加したところが大きかった。基礎医学研究や臨床研究はかなり多額の資金が動くこともあり、かなり遅れを取っており正直言って日本が世界にもたらすことができるものは少ない(分野にもよるので一概には言えないが)。したがって国際会議でも「勉強させていただいています」というお客様のような雰囲気になることがあった。しかし、AAMIではお互いのよいところでコラボレーションし、日本の立ち位置が非常に良かった。またそれだけではない。日本の臨床工学技士は世界的に見れば究極のgeneralistであり、その幅広さにひかれている関係者が予想以上に多いことが分かった。学部三年次にアジア臨床工学フォーラムでもこのことは感じていたが、アメリカという大きな国でそれを感じたことは非常に大きなことだったように思う。やはりこのような日本の臨床工学技士の制度を守り、よりよくしていきたいと感じ、そのためにどうしたらいいか考えるようになった。博士修了後の道として養成校の教員として引き続き臨床工学を盛り上げていくことはこれまでも考えていたが、さらにその気持ちを強めることになった。
さらにいうなら、できれば多くの人にこの経験をしてほしいと思っている。海外での日本の立ち位置を知ることは、仕事のモチベーションだけではなく自分自身の知識として非常に大切なことだ。だからこそこんなに長い文章を書いてなるべく皆さんに詳細を伝えようとしているわけだが、どうだろうか。英語ができなくてもまず話そうとすれば何とかなる(バネラさんの心労は察するに余りあるが)ので、今後のキャリアに悩んだら行くべきだと思う。ただかなり金銭的な負担があるのは事実なので、あこがれたら金銭的な準備はお忘れなく。AAMIのスカラシップもあるのでそちらの応募もぜひ検討しながら、計画的な準備をおすすめする。
最後にこのような機会を頂いた日本臨床工学技士会国際交流委員会の皆様や費用を補助してくださった日本臨床工学技士会、またJST、現地でのアテンドをしてくださったバネラ長澤駐在員に改めて感謝申し上げる。